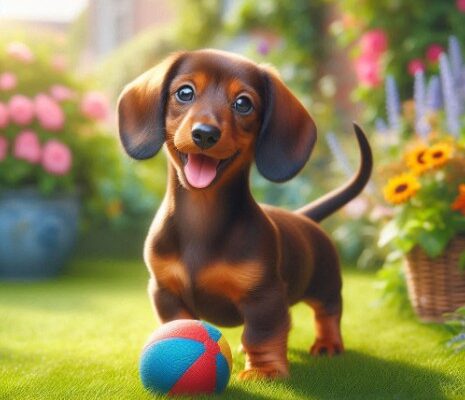「トキソプラズマ症って猫の病気じゃないの?」と思っている方も多いかもしれません。でも実は、犬にも感染する可能性があるんです。
今回は、犬のトキソプラズマ症の症状や感染経路、治療法、そして大切な予防のポイントについて、やさしくご紹介します🐶✨
🦠 トキソプラズマ症ってどんな病気?
トキソプラズマ症は、「トキソプラズマ・ゴンディ」という原虫が体に寄生することで起こる感染症です。猫の病気というイメージが強いですが、実は**人や犬、鳥など、さまざまな動物に感染する人獣共通感染症(ズーノーシス)**です。
犬の場合、主に口から感染します。たとえば:
-
🥩 感染した生肉(豚肉・鶏肉など)を食べた
-
🐈 感染している猫の便をなめた
-
🍽 生肉を調理したまな板で切った野菜をそのまま食べた
このようなことが感染のきっかけになります。
⚠️ トキソプラズマ症の症状って?
犬が感染しても、多くの場合は症状が出ません。でも、免疫力が下がっているときや、子犬の場合は注意が必要です。
主な症状はこんな感じ👇
-
🌡 発熱
-
💨 呼吸が荒くなる(肺炎)
-
🤒 元気がない、だるそう
-
🤢 下痢
-
⚡ 痙攣(けいれん)
-
🧠 脳炎による神経症状
-
🤰 妊娠中の母犬では流産や死産のリスク
ほとんどの犬は無症状ですが、免疫が弱い子は重症化することもあるので、少しでも変化を感じたら早めに病院で診てもらいましょう。

🔍 感染の原因と経路は?
感染のルートは、ほとんどが**経口感染(口から入る)**です。
具体的にはこんなケースがあります👇
-
🍖 生焼けの肉や生肉を与えてしまった
-
🧼 感染した猫のフンに触れた後に足をなめた
-
🥗 生肉を扱った器具で野菜を切って、そのまま食べた
🐕 犬自身はトキソプラズマを排出しませんが、感染源を体に取り込むリスクはあるため、猫と同居している家庭やアウトドアで動物を追いかける子は注意が必要です。
💊 治療はどうするの?
トキソプラズマ症と診断されたら、抗生剤で治療します。
また、以下のような症状がある場合は**対症療法(症状を和らげる治療)**も並行して行います👇
-
解熱剤で熱を下げる
-
点滴で脱水を防ぐ
-
痙攣を抑える薬を使う など
基本的には命に関わることは少ないですが、治療が遅れると重症化することもあるため、油断せずに対応しましょう。
🛡️ トキソプラズマ症の予防法は?
完全な予防は難しいですが、日常生活の中でできる対策を知っておくことが大切です。
✅ これで予防!
-
🐾 感染した猫のフンに近づけないようにする
-
🥩 犬に生肉や加熱不足の肉を与えない
-
🧽 調理器具は使い分け、しっかり洗浄する
-
🧼 散歩後は足や口元をきれいに拭いてあげる
とくに免疫力の低い犬や妊娠中の犬がいる場合は、十分に気をつけましょう。

🐶 まとめ|「無症状だから大丈夫」と思わず、予防をしっかりと!
犬のトキソプラズマ症は軽いケースが多いですが、免疫が下がっていると命にかかわることも。日ごろから次のポイントを意識しましょう👇
-
👅 生肉や感染源に触れさせない
-
🩺 いつもと違う様子を見逃さず、早めの受診
-
🧽 清潔な環境を保つことも大切
家族の一員である愛犬を守るために、日常のちょっとした習慣から予防を始めてみてくださいね🐕❤️
さらに参照してください:犬の僧帽弁閉鎖不全症とは?原因・症状・治療・予防をやさしく解説!