愛犬の様子が「なんだか元気がない」「水をたくさん飲む」「お腹がふくらんでいる」など気になるとき、それはもしかしたら**子宮蓄膿症(しきゅうちくのうしょう)**かもしれません。
この病気は放っておくと命に関わることもあるため、早期発見・早期治療がとても大切です。
この記事では、犬の子宮蓄膿症の症状・原因・治療法・予防法について、わかりやすく解説します🐾
🧪 子宮蓄膿症ってどんな病気?
子宮蓄膿症は、子宮の中に膿(うみ)がたまる感染症です。
細菌が子宮内に侵入し、炎症を起こすことで膿がたまり、命に関わる深刻な状態になることもあります。
特に、中高齢のメス犬や、避妊手術をしていない子に多く見られる病気です。
⚠️ 子宮蓄膿症の主な症状は?
初期はわかりづらいこともありますが、次のような変化が見られたら要注意です。
🐕 よくある症状
-
外陰部から膿のようなおりものが出る
-
水をたくさん飲む
-
おしっこの量が増える(多尿)
-
食欲がない
-
元気がない・疲れやすい
-
吐く(嘔吐)・下痢をする
-
お腹がふくらんでいる
-
発熱する
🧨 症状が進行すると、尿毒症や腎不全などの重大な合併症を引き起こすこともあります。
見逃さず、すぐに動物病院で診てもらいましょう!
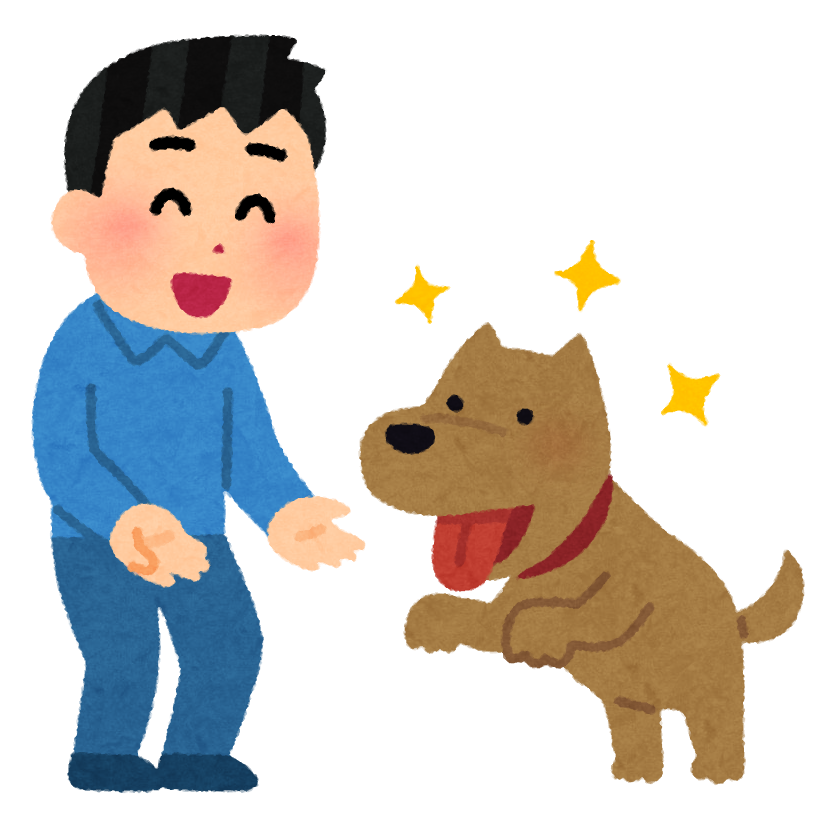
🦠 原因は「子宮の細菌感染」
子宮蓄膿症の主な原因は、子宮への細菌感染です。
特に発情期の後や、ホルモンバランスが乱れやすい老犬に多く見られます。
以下のような細菌が関与しています👇
-
大腸菌
-
ブドウ球菌
-
連鎖球菌 など
💡細菌が入り込みやすいタイミングや体調の変化が、病気を引き起こすきっかけになります。
🛠️ 子宮蓄膿症の治療法は?
治療の基本は、外科手術による子宮と卵巣の摘出です。
膿がたまった子宮を体内に残しておくと命に関わるため、早急な処置が必要になります。
✂️ 主な治療方法
-
外科手術:感染した子宮を取り除く方法が最も一般的で確実
-
内科治療:ごくまれに抗生物質やホルモン剤で膿を排出させる場合もある(※再発リスクが高め)
手術を受ける前には、血液検査・レントゲン・超音波検査などで状態をしっかり確認します。
🛡️ 予防には「避妊手術」が有効!
子宮蓄膿症は、適切なタイミングで避妊手術を行えば予防できる病気です。
✅ 避妊手術のメリット
-
子宮蓄膿症の予防
-
乳腺腫瘍(乳がん)のリスク低下
-
ホルモン関連疾患の予防にも効果的
🐶将来的な病気のリスクを減らすためにも、若いうちに避妊手術を検討するのがおすすめです。
不安な場合は、獣医さんとよく相談して決めましょう。

🩺 まとめ|早めの受診が命を守るカギ!
子宮蓄膿症は、初期には気づきにくく、見過ごしてしまうこともあります。
でも、放置すると命に関わる深刻な状態になる病気です。
🐾 愛犬を守るためにできること
-
日ごろから体調の変化に敏感になる
-
発情後の行動や体調のチェックを欠かさない
-
少しでも気になる症状があれば、すぐに動物病院へ
-
予防として避妊手術を検討する
「いつもとちょっと違うかも…?」と思ったら、それは大切なサインかもしれません。
大切な家族の命を守るために、早めの行動がなにより大切です💖
さらに参照してください:犬の緑内障とは?症状・原因・治療法をやさしく解説!




