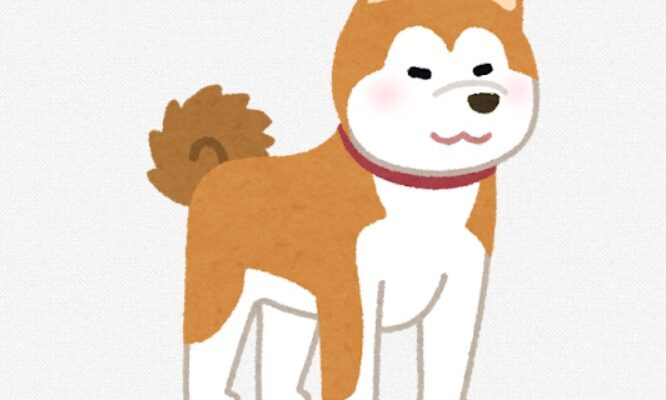愛犬のお尻の調子がいつもと違うと感じたら、肛門嚢炎の可能性もあります。今回は、犬の肛門嚢炎について、症状、原因、治療方法、そして予防策を分かりやすく解説します。日々のケアに役立つ情報が満載ですので、ぜひ参考にしてください!
🐶 肛門嚢炎とは?
肛門嚢炎は、犬のお尻の近くにある肛門嚢(こうもんのう)に炎症が起こる病気です。
肛門嚢は、犬が自分の分泌物(におい)を便に付けるための「におい袋」で、通常は健康状態を保っていますが、細菌感染や排出障害が原因で炎症を起こすことがあります。
⚠️ 主な症状
肛門嚢炎になると、以下のような症状が見られます:
- お尻をかゆがる
犬がお尻を床にこすりつけることが多くなります。 - お尻をなめる
自分のお尻をしつこくなめるしぐさが見られます。 - しっぽを追うような動作
痛みや不快感から、しっぽを追いかけるような行動を示すこともあります。
症状が進行すると、肛門周辺が腫れて激しい痛みを伴い、触られると嫌がったり、排便に支障が出たりすることも。さらに悪化すると、肛門嚢が破れて膿や血液が混じった液体が出ることもあります。
🧬 肛門嚢炎の原因
肛門嚢炎は、以下のような原因で発症することが多いです:
- 排出障害
老化などにより、肛門嚢をしっかりと絞る力(括約筋の収縮力)が低下すると、分泌物がたまりやすくなります。 - 細菌感染
下痢や軟便で肛門周囲が汚れると、細菌が侵入しやすくなり、炎症を引き起こします。
これらの原因が重なり、肛門嚢が詰まり、炎症が発生するのです。
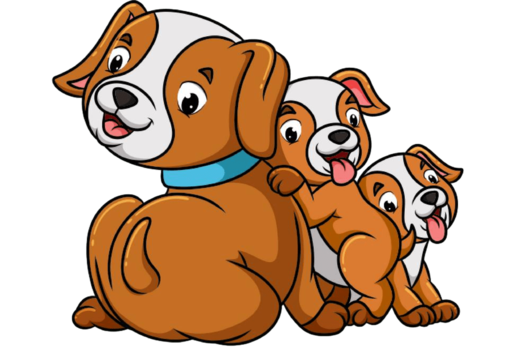
💊 治療方法
肛門嚢炎の治療は、早期発見と適切なケアが大切です。治療法は以下の通りです:
- 肛門嚢の排出
専門家による手技で肛門嚢を絞り、内部の分泌物を排出します。 - 洗浄と消毒
排出後、消毒液や抗生剤を使って患部を洗浄し、細菌感染を防ぎます。
場合によっては、痛み止めなどの追加治療が行われることもあります。早期に対処することで、痛みや炎症の悪化を防ぐことができます。
✅ 予防策
肛門嚢炎を予防するためには、普段からのケアが重要です。以下のポイントを実践しましょう:
- 定期的な肛門嚢の絞り
シャンプーやグルーミング時に、獣医師やトリマーに依頼して肛門嚢を排出させる習慣をつける。 - 肛門周辺の清潔保持
特に下痢や軟便が続いた場合は、肛門周囲を清潔に保つよう注意する。 - 日常の観察
お尻を床にこすりつける、しっぽを追うなどの行動が増えたら、早めにチェックする。
これらの日常ケアにより、肛門嚢炎の初期症状を見逃さず、早期治療につなげることができます。

📝 まとめ
犬の肛門嚢炎は、命に関わる病気ではありませんが、放置すると痛みや不快感が増し、生活の質が低下します。
日頃から肛門周辺のケアを怠らず、異変を感じたらすぐに動物病院で診てもらうことが大切です。
愛犬が快適に過ごせるよう、定期的なケアと観察を心がけましょう🐕💕
さらに参照してください:犬の前立腺腫瘍とは?症状・原因・治療法をわかりやすく解説